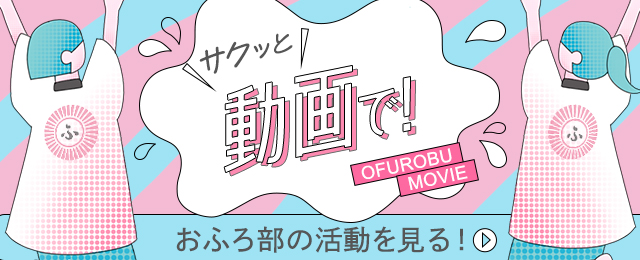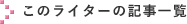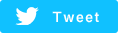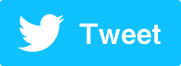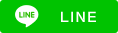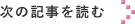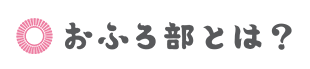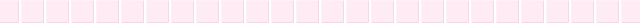

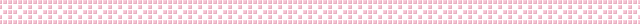

こんにちは!
ぽんちゃんです!
皆さん、サウナはお好きでしょうか?♨
私はサウナが大好きで、大学時代は地元の親友たちと集まっては、サウナに行っており大事な思い出の一つでもあります。
休日や「今日は少し疲れたな、、、」みたいな時にも一人でサウナによく行っておりました。サウナに入っている間って嫌な事全部忘れて、世界が素晴らしく綺麗に感じるんですよね…。
もちろん現実でも世界は素晴らしく綺麗ですよ???
というわけで、今回はぽんちゃん流のサウナ作法をお教えしたいと思います!

とはいえ、特にオリジナリティがある訳ではなくスタンダードですが、サウナに入られたことがない方は是非参考にしてみてください!
まずは基本的なサウナの流れをおさらいします。
- 1.サウナで体を温める。
- 2.水風呂に入る。
- 3.外気欲を浴びて「ととのう」。
これがざっくりと基本的な流れだと思います!
これを踏まえたうえで、ぽんちゃん流サウナ作法行ってみましょう!
①体は十分に温めてからサウナに入る
冬にサウナに入るとなると、冷えた体をサウナで温めたい!と思う方もいらっしゃるかと思います。
しかし!
それではサウナに入って、体が温まるまでの時間がもったいない!体を温めるなら浴槽が一番です!
②出来るだけ上段に、出来るだけ限界まで
これに関しては無理にとは言わないので、自分に合った方法を探してください!
とはいえ、極上の「ととのい」を味わいたい場合は妥協はなしです!
甘い気持ちではなく常に全力でサウナに挑んでください。
上段に、というのは皆さんも小学校の理科の授業で習ったはずの、「温かい空気は上に昇る」というのが理由です。より暑く、より汗のかける上段がおすすめです。
時間に関しても、やはり限界まで追い込んだ方が、外気浴の際の「ととのい」をより感じられると思います。
③水風呂に入る前に、コールドシャワーを!
水風呂に入る前に汗を流すのは、サウナ―としては当たり前。というか人として当たり前ですよね。
しかし、ここで普通の温かいシャワーを浴びて水風呂に足からゆっくり浸かってしまっていては、せっかくサウナで自分を追い込んだのに冷めてしまいます。もったいない。
例によって極上の「ととのい」を感じたいのであれば、汗を流すシャワーですらコールド!コールドシャワーで冷たさに体を慣れさせてから、ザブンと一気に浸かる!

もう既にお気づきかもしれませんが、先ほどの「体を温めてからサウナに入る」も「汗を流すのはコールドシャワーで」も科学的根拠は一切ございません。気持ちの問題です。🔥
④水風呂は「天使の羽衣」をまとうまで!
ここは最も妥協できないポイントです。人によっては、「サウナの暑さより水風呂に入る方が苦手」という方もいらっしゃるかと思います。が!ここだけは妥協できません。
サウナでどれだけ追い込んだとしてもここで妥協していては極上の「ととのい」は得られません。
水風呂は冷たいです。当たり前です。しかし、しばらく浸かっていると、自分の体に膜が張ったような感覚になり、あまり冷たく感じなくなってきます。この膜のような感覚こそが「天使の羽衣」の正体です。この呼び方には地域差があるようで、一般的には「羽衣」と呼ばれているみたいですね。
冷静に考えて、天使って羽衣羽織ってないですよね。どっちかと言うと天女か。
そこまでしっかり浸かって、ついに外気浴で「ととのい」に行きましょう!
※羽衣をまとってからも浸かり続けると、絶対に体にはよくないので、ほどほどに。
⑤ついに「ととのい」
ここまでこれば言う事はありません。思う存分「ととのう」を楽しんでください
少しぽんちゃん流をお伝えするとすれば、よくスーパー銭湯などにあるビーチチェアはおすすめしないという事。
こういうの↓

できるだけ頭を上げずに寝転ぶ事。そして目を閉じ、何も考えない。水の音だけを感じる。普段より五感が研ぎ澄まされたような感覚に陥ると思います。時には世界が自分中心にグルグル回っているように感じる事もあります。
これこそが「ととのい」です。
あとはこれを3セット。
私は1回毎に追い込み過ぎて3セット行く前にととのいきってしまう事がしばしばありますが、これも本物のサウナ―にとっては妥協なのかも知れませんね。
これまで限界まで追い込め!妥協はなし!と散々述べてきましたが、もちろん個人差がありますし、危険が伴う場合もあります。
自分の体と相談しながら、自分にあった「ととのい」を感じてみてください。
おっと、大事な事を忘れていました。
サウナに入るときは水分補給を忘れずに!

私はサウナ中は水、サウナ後は瓶牛乳の一択です。🥛
友達と奢りじゃんけんをしたのもいい思い出。
その後はそのまま友人宅で麻雀を。🀄サウナ代をここで…。
おっと、誰か来たようです…。
それでは。
↓↓↓合わせてこちらの記事もご覧ください↓↓↓
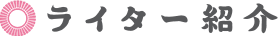
編集部おふろ部
おふろ好きを増やし、おふろを「持続可能な文化」として継続していくため、給湯器などの製品を国内外に展開する住宅設備機器メーカーであるノーリツがおふろのプロとして運営しています。薬機法管理者の観点からも安全で信頼できるお役立ち情報を届けするとともに、おふろ部の活動についても発信していきます!