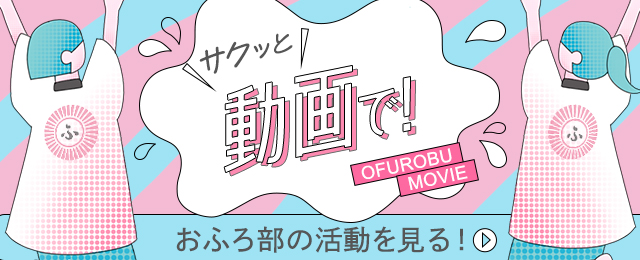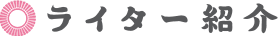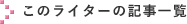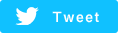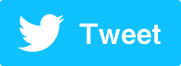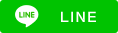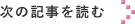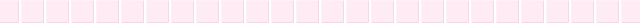

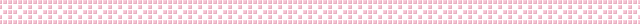

*これは、とあるお風呂好きが書いたお風呂をテーマにした短編小説です。
1.ことの始まり
今日〆切の記事を書き終え、パソコンを閉じる。
しばらく平日の満員電車に揺られ、帰宅しシャワーを浴びる。
私は濡れた髪を手際よくタオルでまとめ、ソファーに体を沈める。
「プルルルル…」
スマホ画面に「ヨコヤマ」の表示。
彼女は大学時代の友人で、社会人になって数年経った今でもよく電話する仲だ。
私は軽やかにスマホを操作し電話に出る。
いつものようにたわいもない世間話をしていたら、ふと彼女はこう言った。
「そういえば私最近さ、会社で湯船利用日数最多賞を取ったんだよねー」
「え~何それ」ボケなの?そんなの聞いたことない。
「それがさ…」ヨコヤマは続ける。なんだか冗談にしては具体的だ。
私は適当に相槌を打ちながらスマホの上で素早く指を動かし検索した。
何やらそれっぽい検索結果。どうやら本当らしい。
私のライター魂に火が付いた。そして次の瞬間にはこう質問していた。
「御社にインタビュー、行っちゃっていい?」
2.インタビュー
翌日の夕方、電車に揺られること約30分でヨコヤマの勤める会社に着いた。
私は受付で彼女を呼んでもらった。
すぐにドアの向こうから彼女が現れ、オフィスを案内してくれる。
彼女の背中に小声で言う。「どこにでもある普通のオフィスって感じなんだけど…」
彼女はくるっと振り返り、いたずらっ子みたいな顔をして言う。
「そう思うでしょ?でも実はうちの会社、社員の湯船利用日数No.1の超ホワイト企業として表彰された、選ばれし会社なのです」
湯船利用日数No.1、超ホワイト企業、表彰…。事前に電話で聞いていたが、いま一度ここで聞いてもピンとこない。
まあそこがライターとしては心が躍るポイントなのだけれど。
私は、ぜひその件についてゆっくりとご教示お願いいたします。と少しおどけて頭をさげた。
ヨコヤマに来客用の席に案内され、腰をおろす。同時に紙とペンを取り出す。
同じ歳くらいの女性社員がお茶を出してくれた。
そつのない慣れた手つきから品の良さが伝わってくる。
私は仕事モードに入り、意図して真剣なまなざしをつくる。
「まず、改めて湯船利用日数No.1って何?ホワイト企業の基準なの?」
ヨコヤマはわざと一口お茶に口を付け、間を取って微笑む。
「そうだよ、まだ知らない人も多いみたいだけど。就活サイトが開発したホワイト企業の基準で、上位に入るとホームページとかでアピールできるの。うちの会社の求人サイトにも最近は記載されてるみたい」
「ホワイト企業の基準ってことは…つまり、湯船に浸かる時間があるってことは、ワークライフバランスが整っているってこと?」
「そのとおり!理解が早くて助かります。仕事が忙しすぎて時間がないと、湯船に浸からずシャワーで済ます人が増えるからね。そこに着目した仕組みってわけ」
私はふむふむ、とメモを取る。彼女は続ける。
「うちは社員が毎日勤怠報告と一緒に昨日湯船に浸かったかどうかも申請するようになっていて。それを集計して、このサービスを管理する就活サイトに提出するの。
すると毎年上位だった企業が発表されて、表彰されることになる。ちょっとしたセレモニーなんかもあるよ。
ちなみに社内でも、四半期ごとに湯船利用日数が高い社員は表彰されるんだ。賞品は入浴剤くらいの物なんだけどね」
その栄えある社員が今回は彼女ってわけらしい。
私はもうちょっと詳しく聞いてみたいと思い質問する。
「御社がいち早く導入したきっかけってなんかあったの?」
「入浴剤を作ってるメーカーさんと取引があった、ていうのもあるみたいだけど。いちばんは社長のおふろ好き、かな。あとは社内で何か新しいことをやってみよう、ていう雰囲気もあって」
さらに質問を重ねる。
「実際、この制度を導入してみてどうだった?」
「噂では湯船に浸かることを推奨したら社員のパフォーマンスもちょっと上がったみたい。それでまた残業時間も減るし、社内でも結構好評よ」
ふむふむふむ。メモを取る。だんだんなんだか良いかもって気がしてきた。
その後20分ほど話を聞き、私は礼を言って彼女のオフィスを後にする。
その時、玄関わきにあるトロフィーがふと目に入った。
そこには「社員湯船利用日数No.1」と書かれたトロフィーが輝いていた。
トロフィーの頂上にはつぶらな瞳をしたアヒルが鎮座していた。

3.そして帰宅
私はいつものソファーに体を沈める。
スマホを手に取り、慣れた手つきでヨコヤマにお礼のLINEを送る。
今日のインタビューをどんな記事にしようか考えながら、コップに注いだばかりの冷えた麦茶を飲む。大きな一息。
今日取ったメモを見返そうとカバンを探ると、硬いものが指に触れた。
そういえばお土産に入浴剤をもらったんだった。
パッケージ越しにほんのりと柑橘系の香りがする。
その夜私は、久しく押していないスイッチを押した。
「お湯張りをします」と音声が流れた。