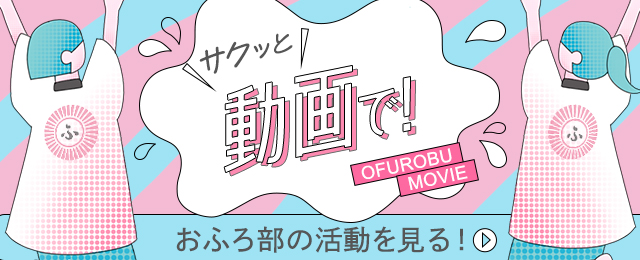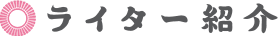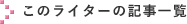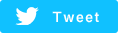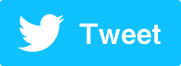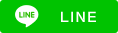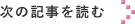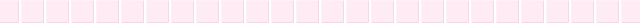

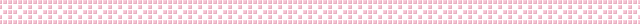

「バスポート」
寒い冬の日だった。辺りが暗くなるのはもう早かった。
仕事の帰り、濱家はコートの前をしっかりしめて、駅からの道を歩いていた。
「今日も早く仕事が終わって良かった……」
歩きながら濱家は呟いた。あまり仕事が遅くなっては、困る事情があったのだ。
駅から少し離れた住宅街は、道を一本中に入ってしまえば人通りはほとんどない。一人細い道を歩いていると、濱家は少し先に、誰かが壁際で椅子に座っているのを見つけた。椅子の前には折りたたみ式の小さな机が置かれており、その上にはランタンの光が灯っている。近づくと、椅子に座っているのは老婆であることがわかった。
……占いか?
たまに、大通りでは占いを見かけることもあったが、こんな場所で珍しい。
濱家は不思議に思いながらも、その前を通り過ぎようとした。その時、机の前に立てかけられた看板に、意外な言葉が書かれているのに気がついた。
「にゅうよく……ざい?」
擦り切れた平仮名で、看板には「にゅうよくざい」と書かれている。机の上に目をやると、色とりどりの石鹸のようなものが並べられている。
「一つどうかね?」
老婆は顔を上げずに、声だけで濱家にすすめた。
「入浴剤か……」
濱家は少しだけ考えてから続けた。
「俺はお風呂は好きだが、あまり家の風呂は入らないんだよな。毎日銭湯に行くようにしてるんだよ。今日もこれから、近所のところに行く予定だ」
それが濱家の日々の楽しみだった。あまり仕事が遅くなると、銭湯は閉まってしまう。いつも早めに帰りたい理由はそれだった。
「そうか、それなら大丈夫じゃ。お風呂に入るのは良い。いい子じゃな」
不気味な婆さんだな、と濱家は思った。いい子だと言われ、子ども扱いされたような気持ちになった濱家は、少し言わなくていいことまで言いたくなった。
「近所にはいくつか銭湯があってな。一つは結構新しい銭湯なんだが、裏口の鍵がいつも空いてるんだよ。だからそこから入れば、いつでも金を払わずに銭湯を使える」
「……」
老婆は濱家の言葉を黙って聞いている。
「他にも、番頭のジジイがちょっとボケてる銭湯もあってな。そこもタイミングを見計らって入ったら、金は払わずに済むんだ。いいだろ」
「……」
「俺はいつもそうやって、タダで使える銭湯を探してるんだ」
「……そんなにお風呂が好きなら、特別なものをあげよう」
しばらく黙っていた老婆は突然そう言った。後ろに置いてあるダンボールから、何かを取り出す。
「これじゃ」
そう言って渡されたのは、紙のカードだった。濱家はそこに書いてある文字を読んでみる。
「……バスポート?」
カードには、確かに「バスポート」と書かれていた。
「そうじゃ。それを見せれば、どんな風呂でも入らせてもらえるようになるんじゃ」
「なんだそれ? こんなジョークグッズも売ってるんだな。いくらするんだ?」
「……あげよう」
「そうか。ま、もらえるならもらっとくよ」
「ただ、注意して使うことだな。そのバスポートは濡れてしまうと……」
「はいはい、ありがとな。今度試しに使ってみるよ」
ボケた婆さんが何か言ってる。そのくらいにしか思わずに、濱家はバスポートをポケットに突っ込んで、そのまま歩いて帰った。
そしてその夜、濱家はいつものように銭湯に向かった。
そして普通の入り口ではなく、裏口から銭湯に忍び込む。いつもしていることなので、別段警戒する気持ちもなかった。しかし、この時はタイミングが悪かった。中に入って数歩進んだところで、偶然にも見回りに来ていた番頭に話しかけられたのだった。
「あれ? 君は、もしかして今裏口から入ってきたのか?」
声をかけられて、濱家は焦った。
「あ、いえ、ちょっと間違えてしまって」
「いや、君はたまにここを使ってるよね。見たことがある。もしかして、いつも裏口から入ってきていたのか」
「いえ、今回だけたまたま入り口を間違えてしまって」
「たまたま裏口から入ったのか? ちょっと、とりあえず警察に通報させてもらうよ」
これはやばいと思った。言い訳を考えながらポケットに手を入れると、何かが指先に当たった。そして濱家は苦し紛れに言った。
「あの、実はこういうものを持っていて……」
とっさにさっきもらったバスポートをポケットから取り出して、番頭に見せる。
「なんだこれは?」
「えっと……バスポートと言いまして」
こんなジョークグッズが通用するはずがない。そう普段なら思うところを、濱家は少しパニックになっていた。しかし、意外な言葉が返ってきた。
「……なんだ、持っているなら早く言ってよ。どうぞ」
バスポートを確認すると、番頭はそのまま何事もなかったように歩いて行った。
残された濱家は、バスポートを手に持って呆然としていた。
銭湯に入りながら、濱家は考えた。まさか、本当にあのカードに効果があるというのだろうか。
濱家は気になって、じっとしていられなかった。少しだけ湯船に浸かると、すぐに銭湯を出た。そして今度は近くの別の銭湯に向かった。そこは昔ながらの銭湯で、おじいさんが番頭をしているところだった。
濱家は、今度は堂々と入り口から入った。番頭に座っているおじいさんは、メガネをかけて新聞を読んでいるところだった。
「すみません、このカードを持ってるんですけど……」
濱家はカードを見せながら話しかけた。おじいさんはメガネに手を当てて、カードに顔を近づける。
「……どうぞ」
そう言って、おじいさんはまた新聞を読みだした。
バスポート。つまりこれは風呂専用のパスポートのようで、どんな風呂も入らせてもらえるようになるカードということらしい。
不思議だ、と濱家は思った。一つの銭湯で使える無料カードならありえるかもしれないが、どんな風呂でも通用するなど、一体どうなっているのだろうか。
とはいえこれを利用しない手はない。せっかくこんな便利なものを持っているのだ。濱家は、もっと値段の高い銭湯に行ってやろうと思った。
早速次の日、隣駅にある様々なサービスが付いているスパにやってきた。元々存在は知っていたが、入場するだけでも結構値段が高いので、これまで行ったことがなかった。まさか、ここも入れるのだろうか。
靴を脱いで受付に行く。横に券売機があるが、そこは無視して受付の女性に話しかけることにした。
「これ、使えますよね」
弱気な態度を見せるのはいけないだろう。濱家は堂々とカードを見せた。
「もちろんです、どうぞ」
女性は当たり前のように、そのまま通してくれた。内心、濱家は小躍りしながら施設の内部へと進んだ。ここでも使えるのか。これはすごいぞ。
館内案内図を見ると、様々な風呂があった。脱衣所の手前には受付の男が立っていて、濱家はそこでもバスポートを見せながら入った。当然止められることはなかった。
最高だ。こんな充実した施設を無料で使えるなんて、やめられない。
浴室には何種類も温泉があった。濱家はそれを手前から順番に浸かっていき、さらにサウナまで楽しんだ。そしてふと、あの老婆のことを思い出した。この不思議なバスポートの仕組みを、教えてもらいに行くべきだろうか。
しかし、こんな便利なものだ。もしかすると返せと言われてしまうかもしれない。誰にも言わずに、使い続けた方がいいに決まっている。
さらに冷え込んだ寒い冬の夜。濱家は駅からの道を歩いていた。
「今日は随分遅くなってしまった」
その日は仕事が遅くなり、近くの銭湯は全て閉まっている時間だった。しかし、ちょうど疲れた時にこそ広い風呂に入りたいものだ。
「何か方法はないだろうか……」
そこでふと、濱家は思いついた。
あの老婆は、これさえあればどんな風呂にも入れると言っていた。ということは……。
帰り道、住宅街の中でも、飛び抜けて高級なマンションがあった。高層ではないが、一つ一つの部屋がとにかくでかいらしい。
濱家はそこのエントランスに入ってみた。とても贅沢な造りになっていて、大きなオートロックの扉の向こうにコンシェルジュがいる窓口があった。
濱家は扉の手前にある集合インターフォンに、適当な部屋の番号を入力して、「呼出」ボタンを押した。ピンポーン、と間延びした音がエントランスに響く。
「はい」
「あの、お風呂に入らせて欲しいんですが」
「はぁ?」
スピーカーから聞こえる男性の声には、明らかに、お前は誰だという怪訝そうな感情が込められていた。
「実はこれを持っていまして」
バスポートをカメラに向けながら、濱家は言った。
「……ああ、どうぞ入ってください。今用意しますね」
ウィーン、とオートロックの大きな扉は開いた。
濱家は、やはり、と確信を得た気持ちだった。
玄関で迎えてくれたのは、身だしなみの綺麗なおじさんだった。
そして案内された風呂は、家の中の風呂とは思えないほどに広かった。脱衣所との間には透明なガラスがはめ込まれている。浴槽にはジャグジーはもちろん、壁に巨大なテレビが埋め込まれていた。金持ちは毎日こんな風呂に入っているのかと驚かされる。
普通に暮らしていては、一生入ることのできないような風呂だろう。それに、このバスポートさえあれば入ることができる。しかも、金持ちが準備までしてくれるのだ。
一生入れない風呂に、もっと入ってやる。
一生入れない風呂……。そこで、濱家は思いついた。
まさかこのバスポートがあれば、女湯に入ることもできるのだろうか。
濱家は隣駅のスパにやってきた。
受付で、バスポートを見せて当たり前のように入る。
そして、男湯と女湯の脱衣場の前にある、もう一つの受付までやってきた。勇気を出して、女湯の方へと足を進める。
「あの、あなたは……」
受付の男に、呼び止められる。
「これを持っていますよ」
濱家はバスポートを見せた。
「あ、そうでしたか。どうぞ」
やはり女湯にも通してもらえるようだった。バスポートの力は絶大だ。
脱衣所には、まだ人はいなかった。だが、男の脱衣所とは違う、少し甘い匂いがする気がする。
服を脱ぎ、バスタオルを巻いて、浴室に向かう。誰かに声をかけられても、すぐにバスポートを見せられるように、濱家は手に持って中に入った。
早い時間に来たせいか、入り口の近くの浴槽には誰もいないようだった。濱家は、とりあえず手前にある浴室に浸かってみる。
そして入り口の方を眺め、誰かが入ってくるのを待っていた。

濱家の興奮は最高潮だった。今女湯に入っている。男の夢が叶っているのだ。
それにしても、このバスポートには一体どんな力が……。
「おっと」
手を滑らせて、湯船の中にバスポートを落とした。すぐに取ろうと濱家が手で掴むと、なんとバスポートは水に溶けるように霧散してしまった。
「や、やばい!」
その時、入り口から何人かの女性の話し声が聞こえてきた。
濱家は焦って、湯船の中に潜った。バスポートがない今、バレたら捕まってしまう。
浴室に入ってきた女性たちは、話しながら奥の方へと歩いて行ったようだった。
もう顔を出していいだろうか。
濱家はおそるおそる湯から顔を出した。
「ひっ」
同じ湯船の中に、誰かが座っていた。
「……濡らすといかんと言ったじゃろう」
あの日、バスポートを渡した老婆が、そこに座っていた。