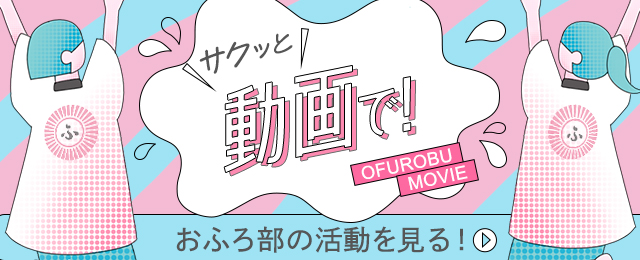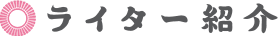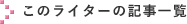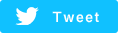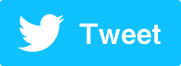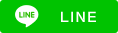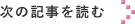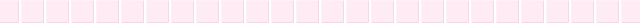

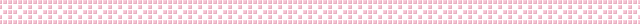
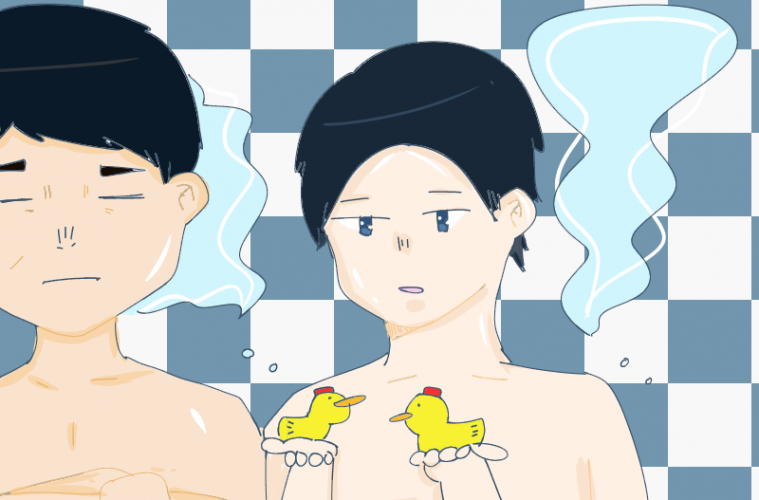
「上田先輩とたかひろくんの、湯るい話」
第一話「広い意味」

老舗の銭湯に、上田先輩とたかひろくんは並んで浸かっていた。
昭和初期に建てられたその銭湯は、どこを切り取っても味がある。
壁に描かれた富士山。オフホワイトのタイルの床。
レモン色の洗面器。
湯気が立ち上り、高い天井から、ポタリと雫が落ちてくる。
「仕事終わりの銭湯っていいっすね」
「そうだな」
浴室に二人の声が静かに響いた。
「……誰もいないっすね」
「この時間は、いつも空いているんだ」
浴槽にも洗い場にも、上田先輩とたかひろくんの二人以外には誰もいなかった。
「上田先輩って、お風呂好きなんすか?」
「……お風呂というより、銭湯が好きだな。どうした?」
「いえ、誰かに銭湯を誘ってもらうって、これまでなかったなって思ったっす」
たかひろくんがここに来るのは、今週だけでも二回目だ。
どちらも、上田先輩に誘われて来たのだった。
「迷惑か?」
「いえ、めっちゃ嬉しいっす」
たかひろくんは首を素早く横に振りながら言った。
たかひろくんが上田先輩から最初に呼び出されたとき、驚いたのは周りの同僚だった。
同僚たちは、たかひろくんが叱られるのだろうと哀れんだ。
何と言っても、上田先輩は寡黙で厳しいことで知られる鉄工所の長なのだ。
当のたかひろくんだけがヘラヘラしていた。
物怖じしない性格……というか、深く考えない性格だった。
そして呼び出しの理由は、意外にも一緒に銭湯に行こうというお誘いだったのだ。
「まさか、上田先輩に銭湯に誘われるなんて思いもしなかったっすよ」
「……」
たかひろくんの言葉に、上田先輩は沈黙で答えた。
普段から無口なのを知っているため、たかひろくんは別段気にしない。
「……銭湯のいいところってなんすかねぇ」
「ゆっくり、色々考えられるところじゃないか」
「色々ってなんすか?」
上田先輩はしばし考えている。
強面のその顔に、深いシワが刻まれた。
他の後輩たちが上田先輩を恐れる理由の一つが、その見た目の怖さだった。
「例えば、こんなにたくさんのお湯が、どこから来たのかな、とかそんなことを思うんだよ」
「この、お湯すか?」
たかひろくんは手のひらで湯をすくってみた。
「そうだ」
「どっかって、あそこからじゃないですか?」
たかひろくんが指差した先には口を開いているトラの像があり、その口からお湯がちょろちょろと出続けている。
古くからその役割を担っているらしく、トラの顔のデコボコはすり減ってつるつるの優しい顔になっていた。
「あのトラがお湯を生み出しているわけではないだろう。その向こう側に、何があるかとかだよ」
「その向こう側っすか?」
「そうだ」
たかひろくんは、トラの口から流れ出てくるお湯をぼんやり眺めていた。
「……上田先輩って面白いっすね。俺、そんなこと考えて銭湯入ったことなかったす」
「そうか?」
「そうっす。なんでお湯って出てくるんすかね」
しばしの沈黙。そして上田先輩がゆっくりと口を開いた。
「昔な、お風呂って、爆発してお湯が温まってると思ってたんだよ」
上田先輩の言葉の意味を、たかひろくんはしばし考えた。
しかし、意味がよくわからなかった。
「どういうことすか?」
「子どもの頃家でな、お湯ためるからガス点けて、とか言われてたんだよ。そういうのあっただろ?」
「それで、爆発するって思ったんすか?」
「だって、ガスだからな」
お湯はトラの口から、ちょろちょろと流れ続けていた。
「……でも、それは危ないから違うよな」
上田先輩は思い直したように言った。
心なしか、少し恥ずかしそうにも見えた。
「そうすね。あ、でも僕も、車はガソリンが爆発して爆風で進んでると思ってました」
「違うのか?」
上田先輩は首をかしげた。
「多分違うと思うす。だって危ないじゃないすか」
「……確かにそうだな」
「多分、ガスだってガソリンだって、爆発するっていうイメージが先行し過ぎなんすよ」
「そうかもしれないな」
銭湯の天井からポタリと雫が一滴落ちて、お湯に波紋をつくった。
「……いや待てよ。考えてみれば、何だって爆発から作られてるんじゃないか?」
「何だってって、なんすか?」
「例えば、宇宙だってそうだろう」
たかひろくんは意味もなく、銭湯の天井を見上げた。
その向こう側にある、広い宇宙を思い浮かべる。
「爆発して宇宙ができて、地球ができて、命が生まれて、俺たちがここにいる。広い意味では、この風呂だって爆発からできたと言っても過言じゃない」
「広い意味ではそうすね」
たかひろくんは納得したように頷いた。
「……でも、実際お風呂ってどうやってできてるんすかね。ボタン押したり蛇口を回したりすればあったかいお湯が出てくるもんで、その仕組みとか考えたこともなかったす」
「確かにな」
「漫画とかで、ドラム缶みたいなやつの下に薪をくべて、お湯を熱くしてるの見たことありますよ。ガスがない頃ってあんな感じだったんすよね」
「……そうか」
そう言って、上田先輩は両手でお湯をすくって、ゆっくり顔を浸した。
「結局あれと同じことを、ガスで火を出してやってるんじゃないか? ガスはガスでも、ガスコンロみたいなものだ。火を点けてる鍋の中でお湯をつくる。つまり、昔と同じことを薪でやるかガスでやるかの違いってだけだな」
「じゃあこの銭湯の下って、火が点いてるんすかね?」
「そうかもな」
「危なくないすか?」
「危ない。でもな、地球だって、真ん中に熱いマグマがあるだろ? それに温められて、地熱とか海流とか、そういうのが生まれたりするわけだ。そう思うと、広い意味では俺たちはいつも風呂の中にいるようなものなんじゃないか」
「広い意味ではそうすね」
たかひろくんは納得したように頷いた。
「その場合、あのトラはなんすかね? 湯が出てきてる」
たかひろくんが指を指した先には、丸みを帯びたトラが、だらしなく開いた口からお湯を垂れ流している。
「飾りだろう」
「そうっすよね」
「世の中、知らないことってたくさんあるっすね」
「そうだな。逆に知っていることの方が少なかったりするんだよ」
「そうすかね」
「考えてみろ。俺たちがここにいるのも、本当かどうか怪しいんだぞ」
「……どういうことすか?」
「つまりな、ここは夢の中だ。今俺と話してるのは、全部お前の夢だ。現実か夢かも、俺たちは知らない。ほら、今日ここに来るまでに、何をしてたかよく覚えてないだろ?」
「え……」
たかひろくんは、不安な顔で少し考える。
「……覚えてますけど」
たかひろくんは真面目な顔で言った。
「だよな」
「怖いこと言わないでほしいっす」
上田先輩は、少し反省したような顔をしている。
「……そろそろあがるか」
「そうっすね」
銭湯は、濃い湯気が立ちのぼっていた。
つづく
第二話「何のために」
老舗の銭湯に、上田先輩とたかひろくんは並んで浸かっていた。
「今日も誰もいないっすね」
「そうだな」
上田先輩に誘われて、たかひろくんは仕事終わりに、よくこの銭湯に来るようになった。
しかしまだ、自分たち以外に客がいるのを見たことがなかった。
「あまり人気ないんすかね」
「これから混むんじゃないか? まだ時間が早いからな」
「そうなんすかねぇ」
上田先輩は周りの部下からは恐れられている。
無口な佇まいと、顔のこわさが理由だった。
しかし本人は、どうして自分が部下から避けられているのかわからなかった。
若者と話が合わない……どこにでもあるようなことだ。
上田先輩にとっては、たかひろくんだけが仕事の現場で普通に接してくれた。
上田先輩はそれが嬉しくて、さらに距離を縮めたくて銭湯に誘ったのだ。
「でもこれ、何なんすか?」
「これって何だ」
「これすよ」
たかひろくんは、湯船に幾つも浮かんでいるその一つを手に取った。
アヒルだった。
今湯船には、数え切れない数のアヒルが浮かんでいる。
「ああ。毎週、水曜日はアヒルが浮いているんだ。入り口にも書いてあっただろ?」
今日はアヒルデー。
そんな張り紙が貼られているのを、たかひろくんも見ていた。
「どうして水曜日にアヒルが浮いてるんすか?」
「そりゃ、店長が浮かべたんだろう」
「そうっすよね。でも、なんのためにって意味っす」
「アヒルが、何のために浮かんでいるかってことか?」
上田先輩は難しい顔をして考えている。
「……癒されるからじゃないか?」
そう言って、上田先輩はアヒルを一つ持ち上げた。
手のひらサイズのアヒルは、黄色一色の体に、目とクチバシがついている。
まつ毛が生えていて、ちょっと間抜けな顔である。
「それなら……あ、今日アヒルデーだから銭湯行くか、ってみんななるんすかね?」
「なるんじゃないか? 火曜日にふと銭湯に行きたくなっても、明日はアヒルデーだから明日にするか、くらいは思うだろう」
「え、上田先輩、アヒル好きなんすか?」
「……」
天井から落ちた水滴が、上手い具合にアヒルの頭の上にはねた。
好きなんだろうな、とたかひろくんは解釈した。
「そもそも、何でアヒルなんすかね? 風呂に浮かべるのは、アヒルって決まりがあるんすか? だって、ハクチョウでもカモでも良いじゃないすか」
「……違うんだよ」
上田先輩は、少しだけ気分を害したように言った。
「っていうか、実はアヒルはカモの仲間なんだよ」
「え、そうだったんすか?」
「そもそもはこれはラバー・ダックと言って、アメリカで流行ったものを輸入したんだ」
「そうだったんすね。上田先輩、物知りっすね」
たかひろくんの言葉に、上田先輩は気を良くした。
「じゃあなんでアヒルは、水に浮くんすかね?」
「……本物のアヒルもな、裏返したらこんな風に空洞になってるんだよ」
「え……」
たかひろくんは、アヒルを一つ裏返してみる。見事なまでに空洞だ。
「……嘘っすよね?」
たかひろくんは真面目な顔で言った。
「そうだな」
「怖い冗談はやめてほしいっす」
上田先輩は、少し反省したようだった。
「……そろそろあがるか」
「そうっすね」
銭湯は、濃い湯気が立ちのぼっていた。
つづく