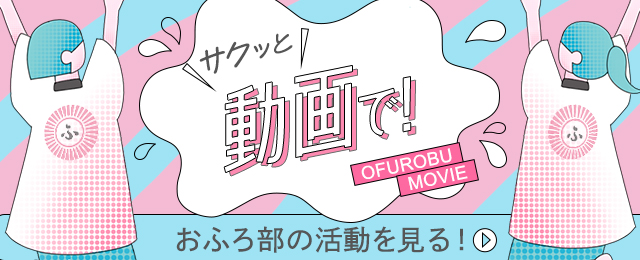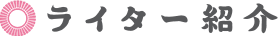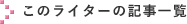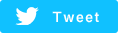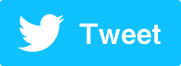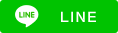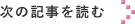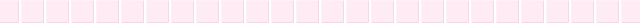

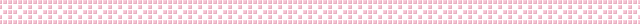

「わんちゃんシャンプー」
「マル、今日はお風呂だぞ」
と、僕が言うと、マルは露骨に嫌そうな顔をする。
犬にも表情ってあるよな、と僕は思う。
マル。
犬種はマルチーズ。
マルをお風呂に入れるのは月に一度だ。
ちゃんとブラッシングして、手玉などをとってから浴室へ連れて行く。
「綺麗にしてやるんだから、そんなに嫌がんなよ」
僕は嫌がるマルを抱きかかえて、浴室へ運ぶ。
「あ、お風呂入れてあげるの?」
廊下に立っていた妹が言った。妹はたまに散歩をしてあげるくらいで、ほとんどマルの世話はしない。
「マル、いつも嫌がってるよね」
「そうだなぁ。子犬の頃から、風呂はそんなに好きじゃなかったっぽいけど」
「シャンプーの匂いが嫌とかあるのかな?」
「んー、普通に濡れるのが嫌なんじゃない。どう?」
とマルに尋ねても、答えるわけがない。
「喋らないから分からないね。シャンプーかえてみたら、嫌がらなくならないかな?」
「新しいの買ってきてくれんの?」
「えー」
そんなやりとりをしながら浴室まで連れて来る。
ここまで来たら、さすがにマルも観念したように大人しくなる。
お尻からぬるいお湯をかけて、体全体を濡らしてあげる。
そして足から順に洗っていく。
そのあと、シャンプーを使って泡立てていく。
その間のマルの顔は、無表情にも不愉快そうにも見える。
ドライヤーで乾かすところまで含めると、結構時間がかかる。
これだけしてあげて、嫌がられるなんて。
一ヶ月後、妹は本当にシャンプーを買ってきた。まさかマルのためにこの妹が何かをするなんて、信じられなかった。
「……何これ? 『わんちゃんおしゃべりシャンプー』?」
それは、今まで見たことのないボトルだった。
「そう。犬の気持ちに寄り添うシャンプーだって。今話題なの。きっとマルも喜ぶよ」
「こんなの使って大丈夫か? ってか、自分でシャンプーしてあげなよ」
「私しないよ。やり方わかんないし」
なんてわがままな妹だ。
でも、せっかく買ってきてくれたんだから、使ってやるか。
僕は嫌がるマルを抱きかかえ、浴室へ行く。
いつも通り体を濡らして、それからシャンプーをつけた。うん、普通に使える。大丈夫だ。
「新しいシャンプーはどう?」
マルにきいてみる。答えるわけがない。
「……悪くないな」
どこからか、低い声が聞こえた。
「え……?」
「まぁ、シャンプー自体が好きじゃないけどな」
僕は驚いて辺りを見渡す。
「だ……誰だ?」
「いや、俺だよ」
僕は手元を見る。まさか、マルが喋っている? 愛らしいその姿からは想像できないような低い声だ。
「喋んの……?」
「早く終わらせろよ。シャンプー、気持ち悪いんだよ」
「わ、わかりました」
僕は急いで、泡を流してあげる。
終わるとマルはブルブル震えて、水滴を浴室中に飛ばす。
そしてもう、喋らない。
ここから、普段ならしっかり拭いてドライヤーをしてあげるのだが……。
僕はもう一度試したくなった。
おしゃべりシャンプーとは一体なんだ。
ボトルからシャンプーを手に出して、マルにつけて泡立てていく。
「……どう?」
と、僕は訊いてみる。
「あのな……」
とまたマルが話し出したので、僕は叫んで妹を呼んだ。
「マルが、マルが喋るぞー!」
「おい、やめろ」
マルは可愛い顔のまま、凄みのある声を出した。
「どしたのお兄ちゃん」
妹がやってきた。
「マルがな、喋るんだよ」
「本当に? マルー」
「……」
何も言わない。まじかこいつ。
「まぁ、そりゃそうだよね」
妹は心配そうな目をこちらに向けて、去っていった。
「おいマル、なんで喋らないんだよ」
「喋ったら面白がってまたシャンプーするだろ? 月に一回だから我慢してるんだ。それ以上したら脱走するからな」
怖い。
僕はすぐに泡を洗い流した。
それから一ヶ月後、またマルにシャンプーをする時期が来た。
「お兄ちゃん、今日は昼からしばらく断水するらしいよ」
まじか。
これは、シャンプーが途中でできなくなり、マルに怒られるフラグが立っている。
「早めにシャンプー終わらせてくる!」
僕はマルを浴室に連れてきた。
この不思議なシャンプー、もっと話題になっていいはずなのに、そこまで世間に知られていない。
シャンプーをしながら、マルに話しかける。
「もしかすると、他の犬も面白がられるのが嫌だから、喋れても喋らないのかな」
「ああー、そうかもな。面倒だしな」
と低い声で答えた。
「こっちは月に一回でも、こうしてマルと話せるのは嬉しいよ」
「それは良かった」
相変わらずぶっきらぼうなやつだ。
「そのシャンプー、試しにお前が使ってみたらどうだ?」
「犬用のシャンプーを?」
「そう。人間が使うと、いいことが起こるぞ」
いいことってなんだろう。
僕は試してみようと思い、シャワーで髪を少し濡らす。
そしてシャンプーを手のひらに出した。
髪につけると、普通に泡立つ。うん、使えなくはない。
そう、言おうとしたところだった。
「ワンワン!」
自分の声が、犬になっていた。
「うわー、マジで使うじゃん」
「ワン!」
「そうそう、人が使うとそうなんのよ。騙されてやんの」
「ワンワン!」

やばい。
僕はすぐに洗い流そうと思った。
急いで蛇口を捻る。
しかし……水が出ない。
「お兄ちゃん、どしたの?」
妹が来た。やばい。
僕は事情を説明する。
「ワンワン!!」
僕の説明は、結構元気な犬の鳴き声になった。
頭にはシャンプーの泡がついたままだ。
「ちゃんと、マルにシャンプーしてあげなよ……」
妹は心配そうな目をこちらに向けて、去っていった。