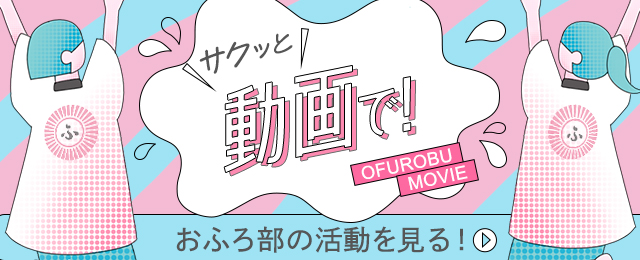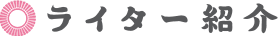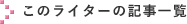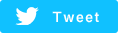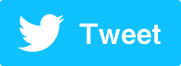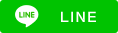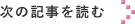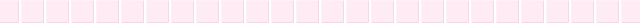

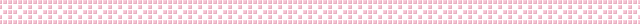

WEAVERのドラマー、そして小説家である河邉徹による、
お風呂をテーマにした不思議で面白いショートショート連載!第1弾!
過去のストーリー作品はこちらから!
河邉徹 ツイッターはこちら!
「にゅうよくざい」
それは寒い冬の日のことだった。
いつものように残業で遅くなった山内は、暗い夜道を家に向かって歩いていた。
ここのところ、遅くまで仕事をする日が続いている。
家に帰っても、さっとシャワーを浴びて寝るだけで、朝が来るとまた会社に行く。
毎日その繰り返しだ。最近は疲れのせいか、寝つきも悪くなってきていた。
短い睡眠では取れなかった疲れが、少しずつ体に蓄積されているようだった。
「海外旅行にでも行けたらいいんだが……そんな時間もお金もないか」
昔は海外旅行が趣味だった。知らない街を歩き、美しい景色に触れると、心が解放されるようだった。
だが、もう長い間そんな余裕はないままだ。転職する勇気もないまま、いい歳になってしまった。
体に冷たい風が吹き付ける。最寄駅から家までの道は、いつもこの時間になるとほとんど人通りがない。
細い路地の左右の塀には、誰かが貼った数枚のチラシが雨風に晒され汚くなっていた。
不動産の広告、脱走したペットの情報。
その中でも、一つ異色なものが山内の目に入った。
[お風呂に浸かりましょう]
手書きで、ただそう一言だけ記された張り紙だった。
張り紙の右下には[風呂]という文字を丸で囲んだ、味のあるロゴのようなものがある。
同じ塀に貼られている他のチラシに比べても新しい。
最近、これに似た広告を電車でも見かけた気がする。どこかの団体が貼っているのだろうか。
疑問に思いながらも、山内がいつものように、途中で一つ角を曲がった時だった。
細い道の先に、誰かが壁際で椅子に座っているのを見つけた。
椅子の前には折りたたみ式の小さな机が置かれており、その上にはランタンの光が小さく灯っている。
少し近づくと、椅子に座っているのは老婆であることがわかった。
……占いか? こんな人気のない場所で店を出すなんて珍しい。
不気味に思いながらも、山内はその前を通り過ぎようとした。
すると机の前に立てかけられた看板に、意外な言葉が書かれているのに気がついた。
「にゅうよく……ざい?」
擦り切れた平仮名で、看板には「にゅうよくざい」と書かれていたのだ。
机の上に目をやると、色とりどりの石鹸のようなものが並べられている。
占いではなかった。あまりに以外だったので、山内は思わず老婆に声をかけた。
「……ここで入浴剤を売っているのか?」
山内が話しかけても、老婆は俯いたまま微動だにしない。
「見ての通り……」
そのままの姿勢で、ただ一言だけそう呟くのだった。
こんなところで入浴剤を売っているだと?
露店で入浴剤を販売しているのなど見たことがない。
あまりに不自然だ。
関わらないほうがいいだろう。
そう思い、山内が背を向けて足を踏み出した時だった。
「……湯船には浸かっとるか?」
後ろからそんな声が聞こえた。自分に向けられた質問だとわかった。
「……いや、ずっと浸かっていないな」
山内は振り返って答えた。
思えば、もう長い間湯船には浸かっていない。
これだけ忙しいと、その時間さえももったいないような気がしてくるのだ。
「……それなら、今日は浸かるとええ」
老婆はこちらに顔を向けるでもなく、そう言った。
つまり、ここにある入浴剤を買えということだろうか。
しかし老婆の言葉は、営業というよりもむしろ、ただ助言をしているかのような響きがあった。
「いい入浴剤なのか?」
「……良質じゃ」
山内は少し好奇心が湧いてきた。
楽しいことのない毎日の中で、こんな場所で入浴剤を買うというのも一つ面白いだろう。
「それなら……これを、一つ」
山内は並べられている入浴剤から、適当に一つを指差して言った。
「ゆっくり浸かりなさい……」
老婆は怪しい笑みを浮かべながら、入浴剤を手にとって差し出した。
家に帰って、山内は早速お湯をため始めた。
いつぶりにお風呂をためるのだろう。
風呂に入る為に待つことなどなかったので、どう過ごしていいのかわからず、脱衣所から湯のかさが増えていくのを眺めていた。
頃合いを見て、山内は買ったばかりの入浴剤を湯船に投げ入れた。
もわもわと泡が立ち、馥郁とした香りが浴槽に広がる。
「……悪くないかもしれないな」
服を脱いで浴室に入ると、気温差のせいか、濃い湯気が立ち込めていた。
足からお湯に浸かると、冷えた足がじんと麻痺したような感覚に包まれる。
ゆっくりと肩まで体を沈めていくと、なめらかな湯ざわりが心地よく、思わず深く息をついた。
久しぶりに浸かった湯船は、どこか懐かしいようでもあった。
夜風で冷えた体が、芯まで温まってくる。入浴剤には温浴効果を高める作用もあるのだろう。
山内は目を閉じて、お湯に体が包まれる感覚を楽しんでいた。
しかしそれからしばらくすると、異変が起こり始めた。
「……なんだ?」
まるで幻覚を見ているように、目の前にどこかの景色が浮かび始めたのだ。

夢か……?
思わず目をこすったが、自分は眠っているわけではない。
山内は湯でバシャバシャと顔を洗った。
それでも、湯気に包まれた浴室の中、景色はどんどん鮮明になっていく。
水辺に立った高い像。立ち並ぶ高層ビル。広い公園。
俺は頭がおかしくなってしまったのか?
山内は大きく首を振ってから、慌てて浴室から飛び出した。
すると、さっきまで見えていた景色は全て消え去って、いつも通りの脱衣所が目の前にあるだけだった。
一体どうしたのだろう。
久しぶりに湯船に浸かったせいで、湯に当てられたのだろうか。それにしても、幻覚など初めて見た。
いや……まさか、あの怪しい入浴剤のせいだろうか。
あの老婆が、おかしな薬でも配合したのかもしれない。
山内は気味が悪くなって、すぐに体を拭いて服を着た。
不思議な気持ちのまま床に就いたが、体はポカポカ温まっていて、その夜はぐっすりと眠ることができた。
次の日、仕事が終わって、山内はすぐに同じ場所へ駆けつけた。
しかし、昨日店があった場所には、店も老婆もいなくなっていた。
怪しい店がなくなって、それでいいはずだった。
そのはずなのに、山内はどこか惜しい気持ちになっていた。
もっとあの入浴剤を使ってみたい。
その夜、山内は入浴剤なしで湯船に浸かってみたが、やはりあの幻を見ることはなかった。
それから一週間が経ち、もうすでに店が現れる期待も薄れてきた頃だった。
帰り道に、いつもの路地を曲がると、以前と同じ場所で老婆が店を出しているのを見つけた。
山内は駆け寄って、老婆に問い詰めた。
「おい、これは一体なんだ?」
「……これとは?」
老婆はまた、微動だにせずに言うのだった。
「この入浴剤のことだ! 何かおかしな薬が入っているのだろう」
「入浴剤?」
「そうだ」
「……これは入浴剤ではない」
「入浴剤ではないだと? それならこれは何なんだ」
「……ニューヨーク剤じゃ」
「ニューヨーク剤……」
山内は慌てて立てかけられた看板を見た。
擦り切れた平仮名で、よく見ると「にゅうよーくざい」と書かれているようにも見える。
「これを入れた湯船に浸かると、ニューヨークの景色が見えるんじゃ」
老婆はことも無げに言った。
山内は驚きながらもふと思った。
なるほど、ぼんやりと見えた景色はニューヨークのものだったのか。
自由の女神、エンパイアステートビル、セントラルパーク。
「しかし……一体どんな仕組みなんだ?」
景色が見える入浴剤など聞いたこともない。いや、ニューヨーク剤なのか。
「それは秘密じゃ」
「そんな怪しいものを売っていいのか?」
「そんなに言うなら、もう店じまいにするかの」
老婆は台の上のニューヨーク剤を片付け始めた。
片付けられていくニューヨーク剤を見ながら、山内はこの前の体験を思い出し、黙ってはいられなかった。
「……待て」
山内の声に老婆は手を止めた。
「なんじゃ?」
「……二週間分もらおう」
老婆は満足そうにニヤリとした。
「ゆっくり浸かりなさい」
山内は袋にいっぱいのニューヨーク剤を持って帰ってきた。
それからというものの、毎晩ゆっくりと湯船に浸かるようになった。
習慣になってしまうと、お湯に浸かることが毎日楽しみになってくる。
湯船の中で、ビルの展望台からの景色を覗き、緑豊かな公園を歩き、ブロードウェイの空気を楽しんだ。
湯気の中で現れる海外の景色は、山内の心を癒した。
なかなか海外旅行に行けず、刺激のなかった生活の中で、心に元気を与えてくれた。
すると不思議なことに、毎晩ぐっすりと眠れるようにもなった。
その結果、日中も仕事に集中できるようになり、気持ちは晴れやかになってきた。
体の中から、力が湧いてくるようだった。
しかし、ニューヨーク剤を一つ、また一つと使うに連れて、湯気の中に現れていた景色は徐々に薄まっていった。
鮮明さを失い、最後の一つを使う頃には、ほとんどニューヨークの景色は見えなくなっていた。
山内は老婆に文句を言うことにした。
その夜、老婆はやはり同じ場所にいたが、なぜかもう片付けを始めていた。
「おい、買ったニューヨーク剤だが、段々景色が見えなくなってきたぞ。不良品じゃないか」
「おお、そろそろ見えなくなる頃じゃと思っておった」
「何だと?」
悪びれずに老婆が言うので、山内は驚いた。
「一体どういうことなんだ」
「……このニューヨーク剤はな、長い間お風呂に浸かっていない者だけが、その景色を見ることができるんじゃ」
「何?」
「これは、お風呂に浸かる習慣のない者が、その習慣を得る為に開発されたものなんじゃ」
説明されても、まだ意味がわからなかった。
「どうしてそんなものを……?」
「お風呂に浸かるのは体にいいことなのじゃ。その証拠に、お風呂に浸かるようになってから、よく眠れるようになったじゃろう? 体温が上がって、心も晴れやかになる。それなのに現代人は、忙しいだの理由をつけてお風呂に浸からん。だからこうして、わしらはお風呂に浸かる習慣を広めているのじゃ」
わしら? どこかの団体なのだろうか? 山内の頭に幾つもの疑問が浮かぶ。
「さて、この地域はお風呂に入る人が随分増えたようじゃな。次の地域に行くとしようかの」
老婆は荷物をまとめ始めた。ニューヨーク剤がどけられた机には、[風呂]という文字を丸で囲んだ味のあるロゴが、大きく描かれていた。