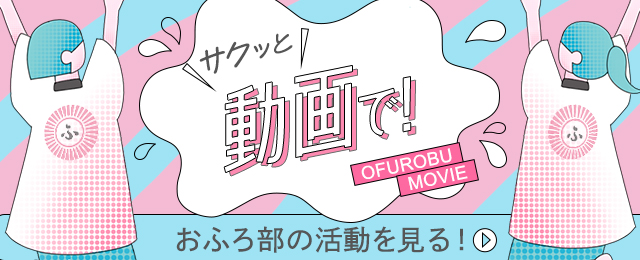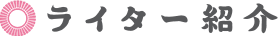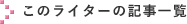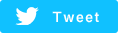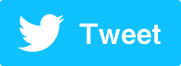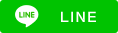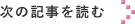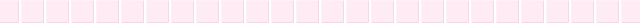

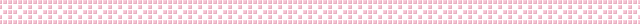

「銭湯Change」
航太郎は小説家だった。
すでに出版された数冊の本が書店に並び、なんとかそれで慎ましくも生活ができるようになっていた。
新作を楽しみにしてくれている読者も、多くはないがいた。
しかしここ三ヶ月ほど、航太郎はまったく物語の続きを書けないでいた。
筆が進まないことはこれまでもあったが、ここまで長い間書けないのは初めての経験であった。
航太郎が今書いているのは、人とロボットが共に暮らす街の物語だ。
それは、航太郎がこれまで書いていた作風とは大きく違うものだった。
新しいジャンルへの挑戦……。そうすることで、読者の幅を広げようと思ったのだ。
しかし想像していたよりも、慣れない話を展開させることは難しかった。
こんなところでつまずいていては、これから先、小説家として暮らしていくことなどできないだろう。
プロはみな、どんな時でも上手く糸口を見つけて書いていくものだ。
そう思い、焦りながらなんとか自分を奮い立たせようとするが、書けないものは書けないのだ。
担当編集者からも、原稿を催促する連絡が来ていた。
「すみません……まだ新しい原稿は書けていません」
そう謝ることも心が痛い。航太郎は自信を失っていた。
自分は小説家に向いていないかもしれない。自分が考えていることには、価値がない。
「それなら……一度銭湯に行ってみるのはどうでしょう?」
担当編集者は意外なことを言った。
「銭湯ですか?」
「そうです。昔から、多くの小説家や作詞家など、アイデアを求めている人たちから愛されている銭湯があるんですよ。試しにちょっと行ってみるのはどうでしょうか」
そんな銭湯があるだなんて初めて聞いた。
航太郎は、藁をも掴む思いでその銭湯に行ってみることにした。
下町にある教えられた銭湯は、想像していたよりもずっと小さかった。
入り口も小さく、地元の人にさえあまり知られていないようだった。
のれんには「Change」と横文字が書かれている。
銭湯らしくない名前だなと思った。
しかし今の航太郎には、まるでこんな自分を変えるための場所のようで、いい名前のように思えた。
入ってすぐ正面に番台があり、右と左で男女の脱衣所が分かれている。
航太郎は番台に立っている、頭に白いタオルを巻いた男に話しかけてみた。
「あの、人に教えられてここに来たんですが……」
「お、何か作ってる人か?」
事情を知っている風だ。
四十代くらいのその男は、体格もよく快活な印象だった。
「はい、小説家をしていまして」
「そうなんだな。まぁ、ゆっくり浸かっていきな。きっといいことがあるよ」
航太郎は壁に貼られた「入浴料金」と書かれた紙を見た。
「大人……三千円?」
高い。見間違いかと思ったが、確かにそう書かれていた。
「客の数が少ないもんでね」
男は当たり前のように言った。
航太郎は少し躊躇したが、わざわざ勧められてきたのだ。
払うしかない。
外からではわからないが、きっと中はとても贅沢な銭湯なのだろう。
千円札を三枚置いて、航太郎は脱衣所に入った。
服を置く場所が四箇所ほどしかない、小さな脱衣所だった。
客が少ないのは本当らしい。
今は他の客もいないようだった。
服を脱いで浴室に入ると、そこにはさして大きくもない湯船が一つと、簡素な洗い場があるだけだった。
値段に見合った設備があるわけでもないようだ。
航太郎は不満に思いながらも、とりあえず洗い場で体を洗った。
それから湯船に浸かってみる。

値段のことは気になったが、払ったものをいつまでも気にするのはよくない。
とりあえず、普段の家の風呂よりは広いこの風呂を、楽しむことにしようと思った。
温かいお湯に浸かっていると、気持ちがほぐれてくる。
リラックスしている時の方がアイデアが出やすいというのは聞いたことがあった。
オフィスや会議室よりも、風呂の方がいいアイデアが浮かぶなんて話もある。
しかし、あの編集担当者はそういうつもりでここを勧めたのだろうか?
ここは昔からクリエイティブな人に愛されていると言っていたが、何か理由があるのだろうか。
しばらく浸かっていると、細身の男が入ってきた。
特に目が合うことも言葉を交わすこともなかったが、わざわざこんなところに三千円も払ってくるのだ。
きっと彼も自分と同じように、小説などを書いているのかもしれない。
値段分楽しもうと思っても、いつまでも湯に浸かり続けているわけにはいかない。
航太郎は細身の男と入れ違いで湯船から出た。
そして真っ直ぐに家に帰り、小説を書くために書斎にこもった。
不思議なことに、いつもよりも集中できた。
いや、ただの集中だけではない。
なぜか物語を書くためのアイデアが次々と出てきた。
自分がこれまで考えていたシーンと新しく思いついたシーンが繋がり、まるで川と川が合流するように一つの物語となって流れ出していく。
形作られていく物語は、すでに人とロボットの話ではなかった。
元々の航太郎の作風通りである、リアルで時にアダルトな男女の物語に変わっていた。
そして作風はこれまで通りだが、そこには自分で考えたとは思えないような、確実に新しいアイデアが組み込まれていた。
「これは……これまでで一番いい作品になるぞ……!」
この筆の進みは、やはりあの銭湯が関わっているように思えた。
航太郎はそれからも、あの銭湯に通った。
少し行き詰まりそうになるたびに足を運び、すると、また新しいアイデアが生まれてくる。
そして無事、航太郎は新しい小説を書き上げたのだった。
本が出版される前に、航太郎は一度あの銭湯に感謝をしたくなった。
「この銭湯のおかげで、新しい作品ができました。本当にありがとうございます」
番台の男にそう伝えると、男は首を横に振った。
「いやいや、礼を言われるようなことでもないよ。実はこっちも助かってるんだ」
「いえ、名前の通り、この銭湯は僕を変えてくれました」
「ああ、Changeってことか?」
「そうです」
「実は、Changeっていうのは、そういう意味じゃないんだ」
「どういうことですか?」
「これは、交換って意味なんだ」
航太郎は男が言っている意味がわからず、首を傾げた。
「あの湯船はな、どういう訳か、入った人たちの間でアイデアが交換されているらしいんだ」
「交換……」
「そう。まるで垢を落とすように、いらないアイデアが湯船の中へこぼれ落ちていく。そして他の人が知らないうちにそれを自分のものにして帰る。あのお湯に浸かってから、何かこれまで考えていたことに、興味を失ったりしなかったか?」
「確かに……」
そう言えば、あんなに人とロボットの話を書こうとしていたのに、そんなものはもうどこかにいっていた。
今思うと、あのアイデアに固執していたから先に進めなかった気がする。
「その代わり、新しいことを思いついたんだろ? いらないものを捨てたら、新しいものを得ることができる。アイデアっていうのはそういうものなのさ」
つまり、航太郎は誰かのアイデアをうまく自分のものと繋げて、一つのアイデアを完成させたということだった。

「交換ってことは……」
「そう。こっちも、湯船にあなたのアイデアをもらってるから助かってるんだ。またよろしくな」
「そうだったんですね」
まさかChangeが変化ではなく、交換という意味だったとは。
「それとな……」
男はこちらをまっすぐ見て言った。
「あんまり、自分をダメだなんて責めなくていいと思うぜ。自分にとっていらないものが、意外にも誰かにとって大切なものだったりするんだよ」
男の見透かしたような目に、航太郎は温かい湯船に浸かったような、じんわりと心が温もるのを感じた。
それから数日後、本屋に行くと自分の小説が大きく展開されていた。
そしてその横に同じくらい大きく、違う誰かの新しい小説が大きく展開されている。
横に貼られた作家の写真を見ると、どこかで見たことある気がした。
そうだ、この細身の男は、あの時銭湯で会った男だ。
その小説のあらすじを見ると、なんと人とロボットが一緒に暮らす街の物語だった。
航太郎は早速それを購入して、家に帰って読んでみた。
小説は、以前自分が書いていたものと設定が似ていた。
しかし、そこに新しい必要なエッセンスが足されて、自分が書いていたものより、ずっと面白いものになっている。
ふと、番台の男が言っていた言葉を思い出す。
――自分にとっていらないものが、意外にも誰かにとって大切なものだったりするんだよ
自分には合わないものや、できないことはある。
しかし逆に、他の人に合わないことが自分に合ったり、簡単にできたりすることもある。
――あんまり、自分をダメだなんて責めなくていいと思うぜ
自分にできることを、しっかり突き詰めていこう。航太郎はそう思った。